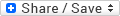Who is it praying for me?
わたしのために祈っているのはだれ?
その方は、もだえ苦しんでゲッセマネで祈っている
ああ、わたしのために祈っているのはだれ?
イエスさまが
柔和で謙遜な救い主が
いのちをかけて、わたしのために祈ってくださる
わたしのために死んでくださったのはだれ?
その方は、痛みのうちにカルバリで死んでくださった
ああ、わたしのために死んでくださったのはだれ?
イエスさまが
贖い主が死んでくださった
自ら進んで、わたしのために死んでくださった
作:R.L.ルスト中佐
出典:The Musical Salvationist, vol.LX, p.10.
On the Cross of Calvary
カルバリの十字架でイエスは死なれた
あなたとわたしのために
そこにて主は、尊い血を流してくださった
わたしたちが罪から解き放たれるために
ああ、罪をきよめる川が流れる
雪のように白く洗う流れが
このわたしのために、イエスは死なれた
カルバリの十字架の上に
カルバリに カルバリに
このわたしのために
イエスは死なれた
カルバリの十字架の上に
ああ、なんと驚くべき愛だろう
わたしはイエスの足もとにひれふす
ああ、死んでくださるほどの愛のゆえに
完全な犠牲が求められている
ここにいま自分自身をあなたにささげます
身も心もすべて、あなたのものです
このわたしのために、あなたは血を流してくださった
カルバリの十字架の上に
カルバリに カルバリに
このわたしのために
イエスは死なれた
カルバリの十字架の上に
作:セーラ・ジーン・グレアム
出典:The Song Book of The Salvation Army, #128.
Here at the Cross
どうしたらあなたに、より良くお仕えできるでしょう、主よ?
あなたはこんなにもわたしに、良くしてくださいました
わたしの働きは、弱く、よろめくものですが
ああ、わたしの生き方であなたの証しができますように!
いまこの聖なる時に
十字架のもとに立っています
生ける力の源である十字架のもとで
わたしは力なく立っています
助けを求めていま立っています
主よ、あなたにお仕えできるように
わたしを変えてください
わたしの耳は鈍くなって、あなたの御声が聴けません
わたしの手は弱くなって、あなたの仕事が果たせません
わたしは足を重く引きずり、カルバリへと続く道に
一歩進み出すことができません
いまこの聖なる時に
十字架のもとに立っています
生ける力の源である十字架のもとで
わたしは力なく立っています
助けを求めていま立っています
主よ、あなたにお仕えできるように
わたしを変えてください
作:ハーバート・ブース、W.A.ウイリアムズ
出典:The Song Book of The Salvation Army, #488.